このツイートを見てほしい。
部長、担当部長、部長役、部次長、副部長、部長代理、特命部長、部長補佐、部長付…部長ヤクマン(笑)。大企業では「部長」と名の付く役職が本物の部長以外に多数ある。副部長代理なんてのも。部長以外に「部長」が大勢いると、決裁権者は一人なのに会議ばかりで意思決定が死ぬほど遅い。
— 木村岳史(東葛人) (@toukatsujin) 2017年4月10日
このような役職名がある組織にいる人、組織にいた人、ビジネス上で付き合いのある人には分かると思うが、この中には部長以外が混ざっている。例えば部長付は明らかに部長未満である。
分かりやすく部長を社長に置き換えてみよう。例えば「社長付」という役職名を見て、「ああこの人社長さんだな」と思う人はいないだろう。部長代理や部長補佐などもそう。多くの組織では部長未満の役職に振られる。
そしてこのツイートの文脈では『「部長」が大勢いる』ということになっている。
このツイートの主はこういう人である。
日経BPには副編集長はいないんだろうか。例えば同社の日経ビジネスオンラインは編集長だらけ、副編集長もいっぱいいるけど。いや編集長だらけで会議大変そうですね。
お役所の、特に中央官庁の課長といえば相当に上の役職である。一方民間では、課長や部長はお役所よりも軽い役職名として使用される。インフレ状態である。
自社のことは棚に上げてこういうのを発信するのはいかがなものかと思う。
部長の脳内で決定するなら10分あれば済む案件が、担当部長といった盲腸役職が多数いると、情報共有と意思のすり合わせのために会議が必要となる。予定調整で会議が1週間後になった挙句、その場で意思決定できず継続案件になる場合も。稟議を上げて資料づくりで残業した部員はただ待たされるだけ。 https://t.co/B9nIxQHbj1
— 木村岳史(東葛人) (@toukatsujin) 2017年4月11日
担当部長が多いと会議が多いのか?そこには正の相関があるのか?データは提示されていない。多分彼の想像上の会社なんだろう。逆に「部長の脳内で10分」というのはどこから来たんだ?
前からこの手のそれっぽいけど誤認しているツイートが多いのでウォッチしている。そしてこの頃は、締めに書くけど言行不一致が加わり突っ込みどころが多くスルー気味。
ヲチ対象に落ちたきっかけはコレである。
システム開発を経営会議で報告する際に「請け負った○○社が責任を持ってやると言っています」と他人事のように言うCIOがいまだに存在する。こういう人は結果に責任を取ろうとしない。プロジェクトが失敗すると「ベンダーを信頼していたのに裏切られた」などと言う。傾いたマンションの話と同じ。
— 木村岳史(東葛人) (@toukatsujin) 2015年11月20日
このツイートの意味するところは、木村氏は経営会議でCIOが発言してる現場にいたか、 経営会議の内容を漏らした役員等がいたかのいずれかということである。自社の話ならそう書くべき。質問してみた。
見たんですか、そういう話が漏れてきたんですか。いずれもその会社まずいですね。 https://t.co/SRCkLoEBYT
— ꧁🐶꧂ (@shigeo_t) 2015年11月20日
ノーリアクションである。この話を上記のように膨らませるのは諦めたらしい。まずいと気付く能力はあった模様。ツイ消ししないだけましだが。
経営会議の内容を出版社の人間が知ってて、軽くツイートできるとか、すげえヤバいじゃん。
— ꧁🐶꧂ (@shigeo_t) 2015年11月20日
こんなのもある。
日本のコンピュータメーカーは二番手戦略だった。とにかく先頭を走る巨人IBMの真似をして追随するのが唯一の戦略。パクリまでやって米国で日本人の逮捕者が出る始末。だが、そのIBMが転んだ。日本メーカーは真似る対象を失い、どうしてよいか分からなくなり、人月商売に逃げ込んで今に至る。
— 木村岳史(東葛人) (@toukatsujin) 2016年3月15日
分野は 木村氏の取材対象である。事実は通商産業省(当時)の指導の元に作られたもので、メーカーの戦略の上に通産省指導がある。
1970年代に当時の通商産業省の指導の元に作られた、日本における3つのコンピュータメーカーのグループ。
当時、日本では汎用コンピュータの開発が欧米に比べ遅れていたため、コンピュータメーカー6社を集め3つのグループを形成した。2社で共同開発を促し、グループ同士に於ける開発競争を促した物。
誤認や知らなかったで済む話ではないので聞いてみた。
メーカーのせいというわけでもないですよ。通産省(当時)の指導ですから。ご存じのお歳かと存じますが。 https://t.co/a31SXC1pQ6 https://t.co/3pjAujM7AA
— ꧁🐶꧂ (@shigeo_t) 2016年3月15日
回答はこちら。
もちろん、知っていますよ。ただ、同じような通産省のグルーピングのご指導を、「ふざけんな」と本田宗一郎が蹴っ飛ばした自動車産業は、超一流の産業に育ちましたが。 https://t.co/SgsSwb1eID
— 木村岳史(東葛人) (@toukatsujin) March 15, 2016
当然こう返すことになる。
だったら文字数も余裕あることですし、書くべきですね。そこを明記しないと、通産の指導の件を知らない人をミスリードすることになりますし。 https://t.co/edpxAGkMji
— ꧁🐶꧂ (@shigeo_t) 2016年3月15日
本田宗一郎の件は知らなかったので今ぐぐってみた。
この構想は、国内自動車メーカー8社を「(1)普通乗用車、(2)高級車、スポーツカー、ディーゼル車、電気自動車などの特殊乗用車、(3)軽自動車」の3つのグループに分けて、各グループが特色を生かした生産体制をとる、というものだった。そのためには、各社が生産の重点を上記3つのうちどれか1つに絞り込み、ほかの部門からは撤退するか、手を出させないようにする必要があった。
当然、通産省のこの構想には自動車業界から「官僚による産業統制ではないか」として猛反発が起こる。そのため、通産省はこの構想を断念せざるをえなかった。
(中略)
そのなかにあって、当時まだオートバイ製造に専念していて乗用車メーカーとしては認められていなかった本田技研の社長・本田宗一郎は通産省に真っ向から勝負を挑む。本田は以前より進めていた四輪車製造開発を、通産省からの中止要請にもかかわらず続行し、同1963年の夏から秋にかけて、軽四輪トラックと小型スポーツカーをあいついで発売したのだ。
大枠では本田宗一郎は通産省案を突っぱねているけど、そもそも他のメーカーも猛反発。本田宗一郎の動きは通産省案の枠外。トリミングする場所がおかしくねえか?
さらにツイートだけでなくこんなのもある。
オレのブックマークコメントはこれ。
GoogleやMicrosoftが大企業ではないと? / “木村岳史の極言暴論! - ITベンダー、ユーザーを問わず大企業の技術者がダメな理由:ITpro” https://t.co/GkrazHWJiW #考察
— ꧁🐶꧂ (@shigeo_t) 2015年11月16日
そしたら「(笑)」付きで帰ってきた。なにがおかしいんだか。
著者の木村です。もちろん大企業ですよ(笑)。ただ、そうした米国ベンダーの技術者は、プログラムをガンガン書くし、ITを使ってどうビジネスをして儲けるかを考えるのも日常。日本の大企業の若手技術者の置かれている状況との差は大きいです。 https://t.co/DzWSc6Tgg1
— 木村岳史(東葛人) (@toukatsujin) 2015年11月16日
当然こう返信することになる。
だったらタイトルには「日本の大企業」と表記すべきですよね。 https://t.co/qvlUyMakMi
— ꧁🐶꧂ (@shigeo_t) 2015年11月16日
ここまで見てわかるように「雑」なんだろう、この人。分解能が低いというか。主語が大きいというか。
ほんの数文字でクォリティはぐっと上がるのだが、最初の発信時点で雑。やりとりしている中でちょっと雑になるのは理解できるが、最初の時点で雑。本業はなんなんでしょうね?
まあ、日経BPは木村氏だけでなく雑で、周回遅れの会社だとは認識しているけど。
JIS X 0701:2005を無視する話は、自社の雑誌名を変えるところから始めてはいかがでしょうか。
技術者の中には「ユーザー」を「ユーザ」、「センター」を「センタ」などと音引きを取りたがる人がいるが、そろそろ止した方がよいと思うぞ。それは昔メモリーなどのリソースが限られていて、データ量を減らすために「メモリ」とした時の発想。今はリソースが豊富なのだから世間に合わせた方がよい。
— 木村岳史(東葛人) (@toukatsujin) 2017年3月9日
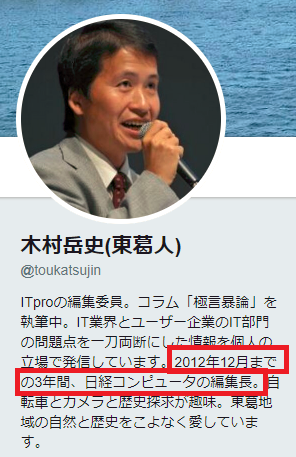
なぜ自分が編集長の時に変えなかった?

日経コンピュータバックナンバーDVD 2015年1月~12月 (<DVDーROM>)
- 作者: 日経コンピュータ
- 出版社/メーカー: 日経BP社
- 発売日: 2016/11
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
